みなさん、こんにちは。アイビディアです。
今日は「PER(株価収益率)だけを頼りに銘柄を選ぶと、成長株のビッグウェーブを見逃すかもしれない」というテーマを、具体例を交えながら改めて解説します。ファンダメンタルズ分析は“決算という事実”をよりどころにできる安心感がありますが、その数字のタイムラグを意識しないと好機を取りこぼしてしまう──これが今回の核心です。
PERが割安=買い、ではないワケ
PERは「株価 ÷ EPS」で求められ、一般的には**“株価を何年分の利益で回収できるか”**を示す指標として親しまれています。数字が小さいほど割安に見えるため「PER○倍以下なら買い」というシンプルなルールを設ける投資家も多いでしょう。ただし、そのロジックには次のような落とし穴があります。
- 株価は未来を先取りする
画期的な新製品や大型契約、規制緩和といったポジティブサプライズが出ると、市場は実現前のキャッシュフローまで織り込んで株を買いにいきます。すると株価は急騰する一方、分母となるEPS(過去実績)は動かないため、PERは一気に跳ね上がります。高PER=危険とは限らず、**“成長期待が株価に表れただけ”**というケースが少なくありません。 - EPSは“決算が確定した過去”の数字
決算発表は遅行指標です。会社が示すガイダンス(業績予想)を使えば多少は未来を反映できますが、ガイダンス策定後に起こった新しいイベントは当然含まれていません。EPSがアップデートされるのは次の決算シーズンまで待つ必要があり、その間に株価とPERだけが先行して動く状況が生まれます。
実例:パランティア(PLTR)に見る“高PER相場”
2024年、S&P500で屈指のリターンを叩き出した**パランティア(PLTR)**は、11月以降ずっとPERが三桁台に張り付いたにもかかわらず株価を伸ばし続けました。「PER30倍以上は買わない」と機械的に除外していた投資家は、このラリーに参加するチャンスすら得られなかったはずです。ポイントは、将来EPSがどれほど伸びるか自分で試算し、その成長ペースを割り引いても株価が妥当かどうかを判断する姿勢にあります。
それでもPERを“捨てない”ための二つの補正軸
- 予想PER(Forward PER)
最新のガイダンスを基に来期のEPSで割り算すれば、過去データ依存という弱点をある程度補えます。とはいえ、ガイダンスに載らない材料が後から出てくることは日常茶飯事。数字を丸のみせず、アップサイドイベントの有無を常にチェックしましょう。 - 業界平均との比較
同業のPERレンジと照らし合わせることで、市場がその銘柄だけに過度な期待を抱いていないかを確認できます。ITハードウェアとSaaSでは許容されるPERがまったく違う──この常識をベースに、高低の判断を下すのが現実的です。
まとめ:成長株を取りこぼさない四つの視点
- PERは“過去と未来のズレ”を抱える入口指標と心得る
- 高PER=危険ではなく、“成長期待の先取り”という可能性を検討
- 将来キャッシュフローを自分で描き、期待成長率とリスクで補正する
- 業界平均や歴史的レンジも参照し、過度な楽観・悲観を排除する
ファンダメンタルズ分析は確かな羅針盤ですが、「過去の数字は未来を映さない」という前提を忘れないことが、グロース株の稲妻をつかむ第一歩です。次回は、私が実際に使っているスクリーニング条件や、決算シーズンで注目する指標を詳しくご紹介します。お楽しみに!
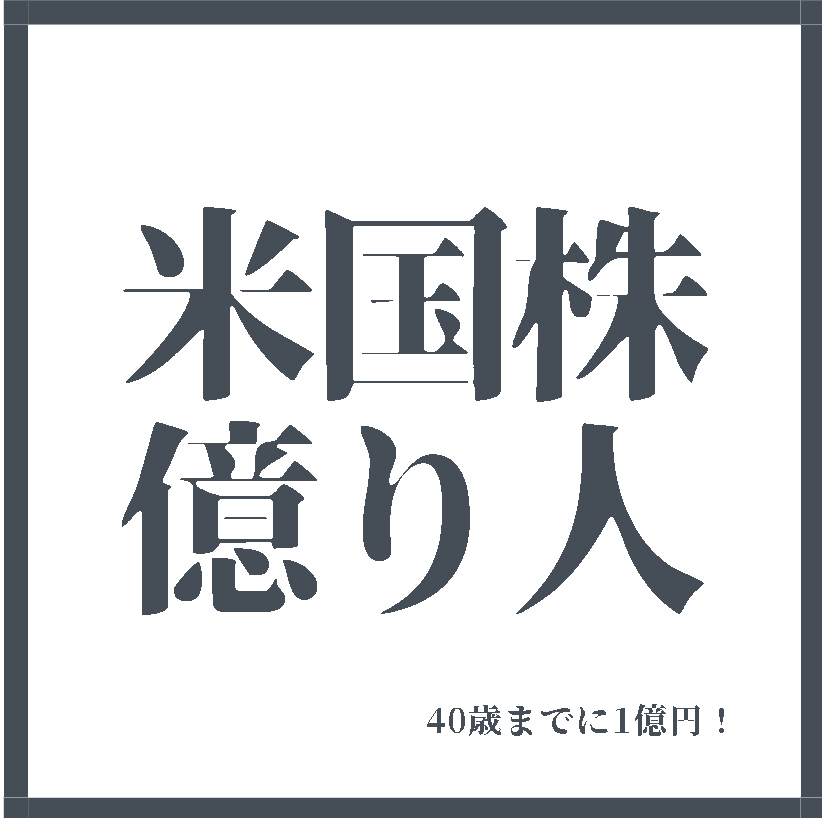


コメント